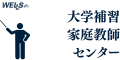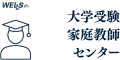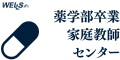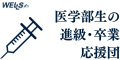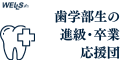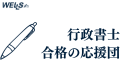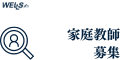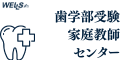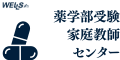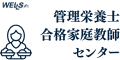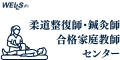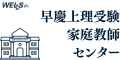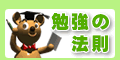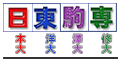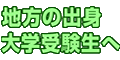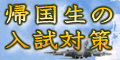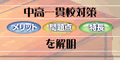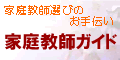はじめての薬剤師国家試験 合格法:無理なく続く学習計画
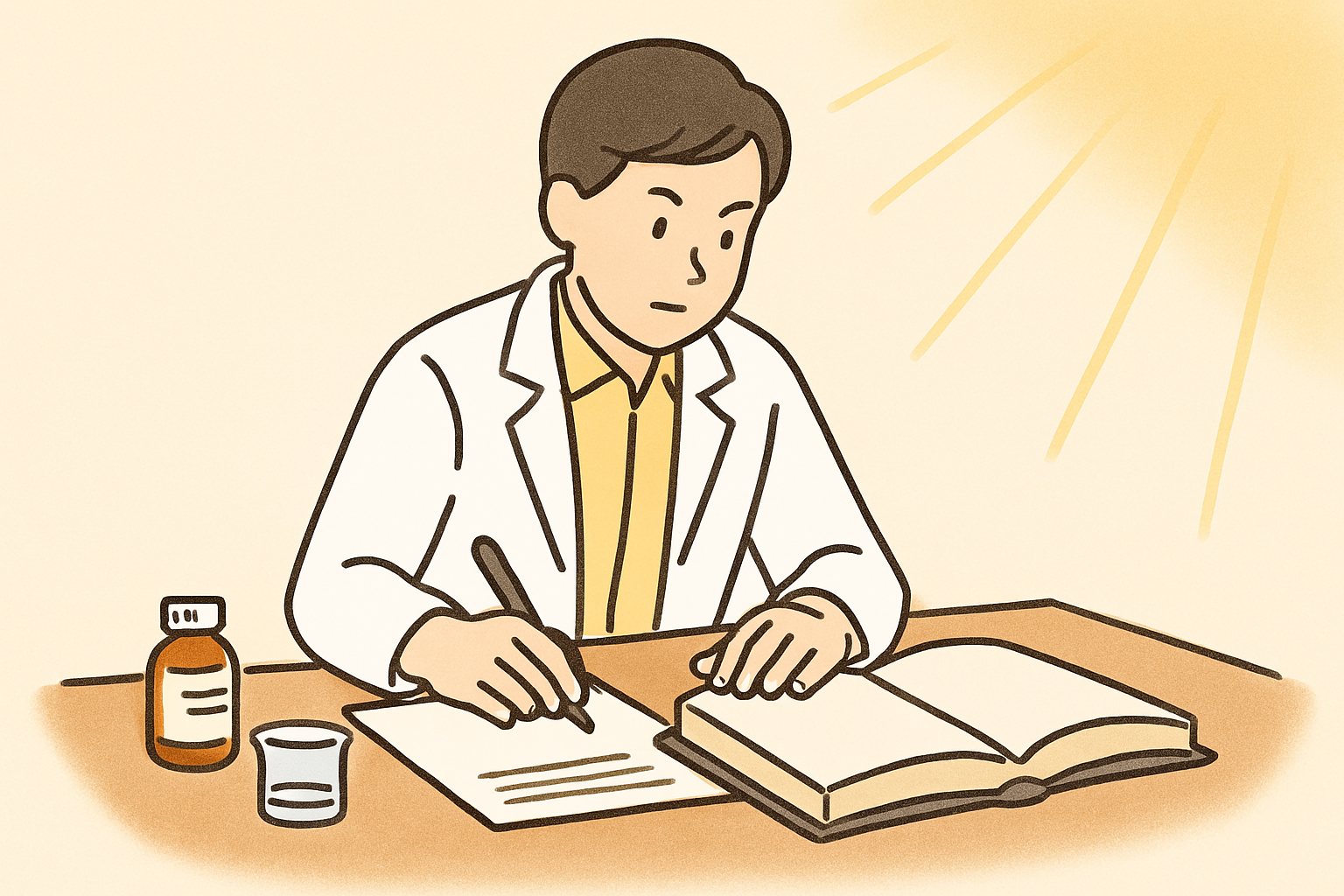
はじめての薬剤師国家試験、不安ですよね。
多くの受験生が同じように不安だと答えています。
でも大丈夫。不安は「準備しよう」というサインです。
いまの弱点を見つけて、一つずつ減らしていきましょう。最後まで油断せず、コツコツ続ければ前に進めます。
- 不安は医療系学生によくある反応です([医療系学生のストレス研究])。「自分だけ」と思わず、準備の合図ととらえて大丈夫です。
- 制度や出題は最新情報を確認してください([厚労省|試験総合][厚労省|出題基準])。結果を保証するものではありませんが、やり方は今日から整えられます。
目次
まず「いまの力」を知る
苦手の直し方(だれでもできる形)
進み具合を見える化する
- 月1回、同じ範囲でミニテスト→正答率の変化を見る。
- うまく上がらない所は、原因を「知識の不足/計算の手順/文章の読み取り」に分け、やり方を入れ替える。
- つらい日は必ず少しだけ:例)1問だけ解く/1分だけ音読。
- 小さな行動を毎日に組み込むと、学習が安定しやすいと報告されています(見える化・振り返りの工夫:[時間管理メタ分析])。
スケジュールは「例」でOK(自分用に直す)
学び方を選ぶ(独学/家庭教師/両方)
- 独学:自由・安い。ただし質問がすぐ解決しにくい。
- 家庭教師:弱点に集中/その場で質問OK。費用や相性の確認が必要。
- 両方:ふだんは独学、月1〜2回だけ点検してもらい、優先順位と疑問を直す。
- まず1週間だけ独学で試す→進みが悪ければ支援を足す。
- 継続の仕組み(定期点検や振り返り)があると、計画が回りやすくなります([時間管理メタ分析])。
- 結果を保証するものではありませんが、やり方は変えられます。
相談相手を一人決める
- 友人・先輩・先生・家庭教師など、話しやすい人を1人。
- 週1回の短い面談(進捗確認・口頭説明)で迷いを早く直す。
- 気持ちが落ちるのは普通。話せる相手がいると戻りが早い。
- 医療系学生では心理的負担が高まりやすいとされるため、相談先の確保は有効です([医療系学生のストレス研究])。
全体の道をそろえる
抜けをふせぐチェック
いちばん大事なポイント
- やる順番は「配点が高い × よく出る × いま間違えやすい」ところから。
- よく出るが間違えにくいところは、短い復習で維持。
- 出題が少なく配点も低いところは、後回しでもOK。
まとめ
参考リンク
- [医療系学生のストレス研究]/PMC(例)/https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10631164/ / https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11574819/、メンターのサポートを活用することが大切です。学部の勉強と試験勉強のバランスを取りながら進め、セルフチェックや第三者のチェックを活用して知識を確実に固めていきましょう。合格に向けて一歩一歩着実に進んでいきましょう。
- [厚労省|試験総合]/厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/yakuzaishi/
- [厚労省|出題基準]/厚生労働省/https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakuzaishi-kokkashiken/index.html
- [テスト効果レビュー]/J-STAGE(日本語レビュー)/https://www.jstage.jst.go.jp/article/sor/62/1/62_1/_pdf/-char/ja
- [間隔反復メタ分析]/PubMed(Cepeda 2006)/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16719566/
- [間隔の最適化]/PubMed(Cepeda 2008)/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19076480/
- [時間管理メタ分析]/PLOS ONE/https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0245066