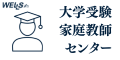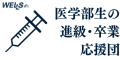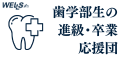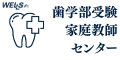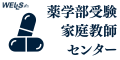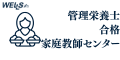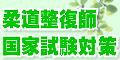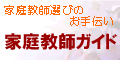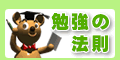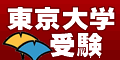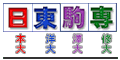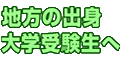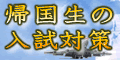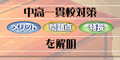【星薬科大学 薬学部 3年生】 基礎科目でのつまずきから進級・卒業への再挑戦
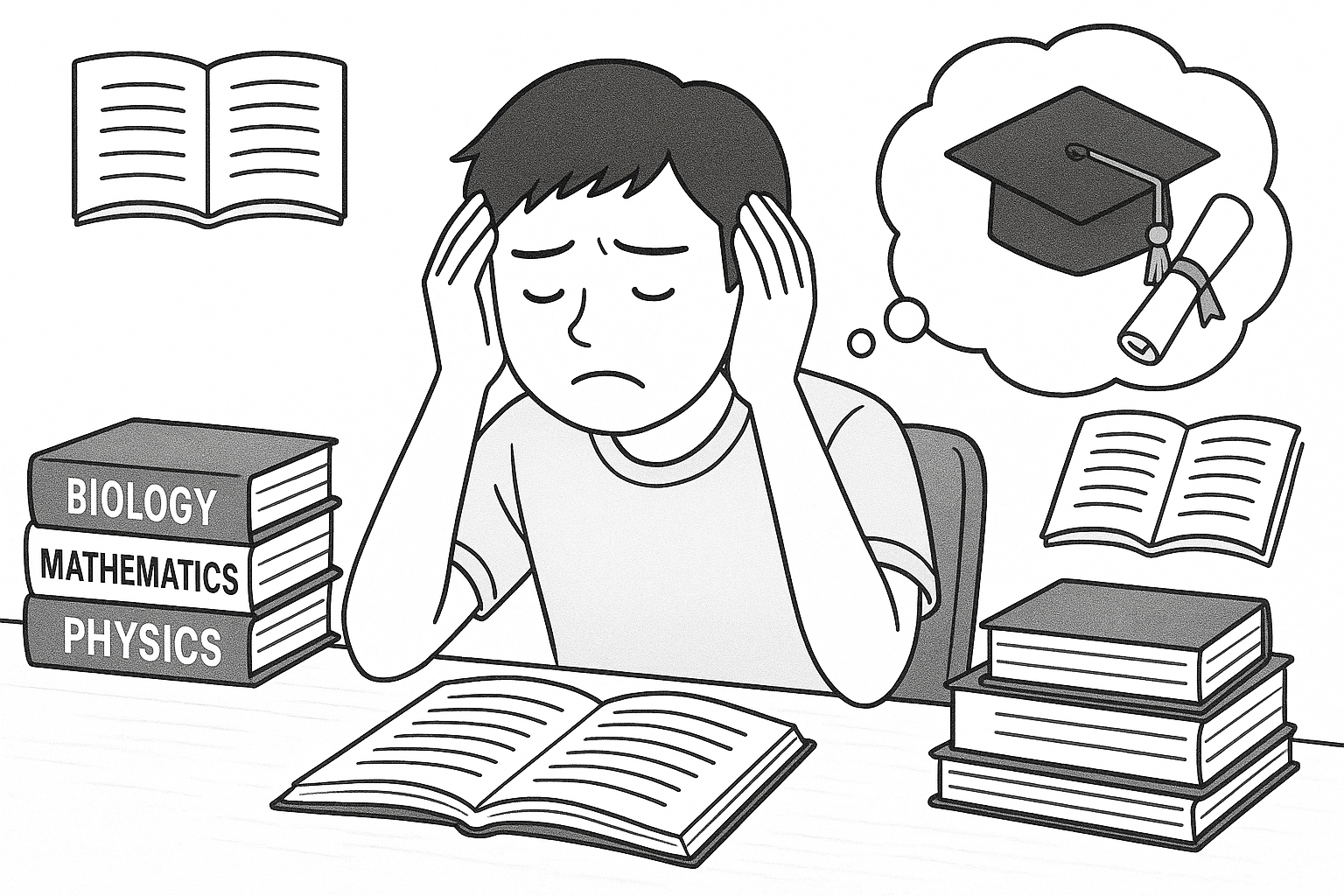
1年次の基礎科目でつまずいて以来、有機化学と物理化学の単位を落としてしまった私は、星薬科大学薬学部の3年生になっても、その遅れを引きずったまま学年を重ねていました。表向きにはなんとか進級しているものの、内心はいつも不安でいっぱい。講義に出ても内容は頭に入らず、ノートには黒板の内容を書き写すだけ。家に帰って見返しても、「これ、何を説明していたんだっけ」と思うばかり。周囲の友人が研究テーマの話をするなか、自分だけが置き去りにされているような感覚がありました。
そんな中、研究室配属が近づいたある日、担当教員から言われた一言が胸に突き刺さりました。
「今のままでは、卒業が難しいかもしれないよ」
その瞬間、胸が締め付けられるような感覚を覚えました。いよいよ現実が動き出してしまった、逃げ場がなくなった――そんな焦りと恐怖が一気に押し寄せてきました。ノートを開いても、教科書のページをめくっても、頭には何も残らない。進級どころか、将来も見えなくなりかけていました。
そんなとき、母の勧めで出会ったのが、ウェルズの家庭教師の先生でした。初回の面談で先生に言われたのは、「まず、基礎概念を一つずつ整理し直そう」という言葉でした。理解できていない自分を否定するのではなく、今からやり直せばいいという姿勢で話してくれたことで、気持ちが少し楽になりました。
指導は週2回の対面授業を軸に、学習計画と日々の進捗管理を組み合わせたスタイルでした。毎週のはじめに「今週やること」「何にどれだけ時間をかけるか」を一緒に決め、毎日の学習時間を記録して進捗を“見える化”する方法を取り入れました。
有機化学では、反応機構を図に描き直し、条件や生成物を言葉にして説明する練習を重ねました。「この反応が起きるのはなぜか」「矢印の向きには意味がある」といった一つひとつの動きを、まるで映像として頭に描くようなイメージで理解していきました。問題集は一冊に絞り、同じ問題を何度も繰り返して、手が自然に動くまで体に染み込ませていきました。
物理化学では、ただ公式を暗記するのではなく、「その式はどこから来たのか」「どういう条件で成立するのか」といった背景を徹底的に掘り下げました。先生は「説明できない知識は、本番では使えない」と言い、どんなに時間がかかっても“わかったふり”を許しませんでした。だからこそ、応用問題に取り組んだときに「あ、これはあの原理だ」と気づく瞬間が増えていき、勉強の手応えがようやくつかめるようになったのです。
学習面だけでなく、メンタル面での支えも非常に大きなものでした。小テストで点が伸びるたびに、「よく頑張ったね」「着実に伸びてるよ」と言葉をかけてもらい、自己肯定感が少しずつ回復していきました。以前はノートを開くのが怖かったのに、今では進捗チェック表に「〇」をつけるのが日課になり、1日の終わりに達成感を持てるようになったのです。
指導開始から4か月後、学内テストで有機化学・物理化学ともに80点を超えたとき、自分でも驚くほど冷静に「やればできるんだ」と思えました。講義室の天井が、いつもより少し高く見えた気がしました。成績だけでなく、視界そのものが変わったような、そんな感覚でした。
進級判定も無事にクリアし、研究室配属が決まった今、「卒業を目指して頑張ろう」という言葉が自然に出るようになりました。もう「落としたらどうしよう」ではなく、「どう活かそうか」と考えられる自分がいます。
あのとき、あの言葉をかけられて、ただ一人で悩み続けていたら――きっと私は途中であきらめていたと思います。知識の積み直しも、生活の立て直しも、一人では限界がある。でも、支えてくれる人がいて、一緒に整理してくれる人がいれば、人は変われる。私はそのことを、身をもって経験しました。
これからは卒業後の進路も見据え、薬剤師として必要な力を一つずつ積み重ねていきたいと思います。過去の自分のように、悩んで立ち止まっている薬学生がいたら、伝えたい。やり直すのに遅すぎることはない。理解は、積み直せば確実に深まる。支えてくれる人がいれば、あなたの未来は、きっと変えられます。