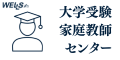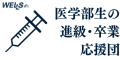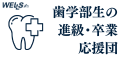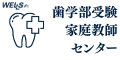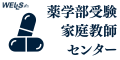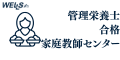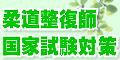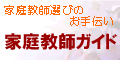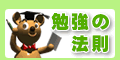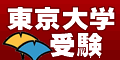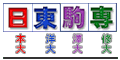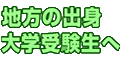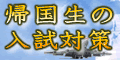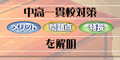【理系未経験 薬学部 2年生】―苦手を乗り越えた6年間の挑戦
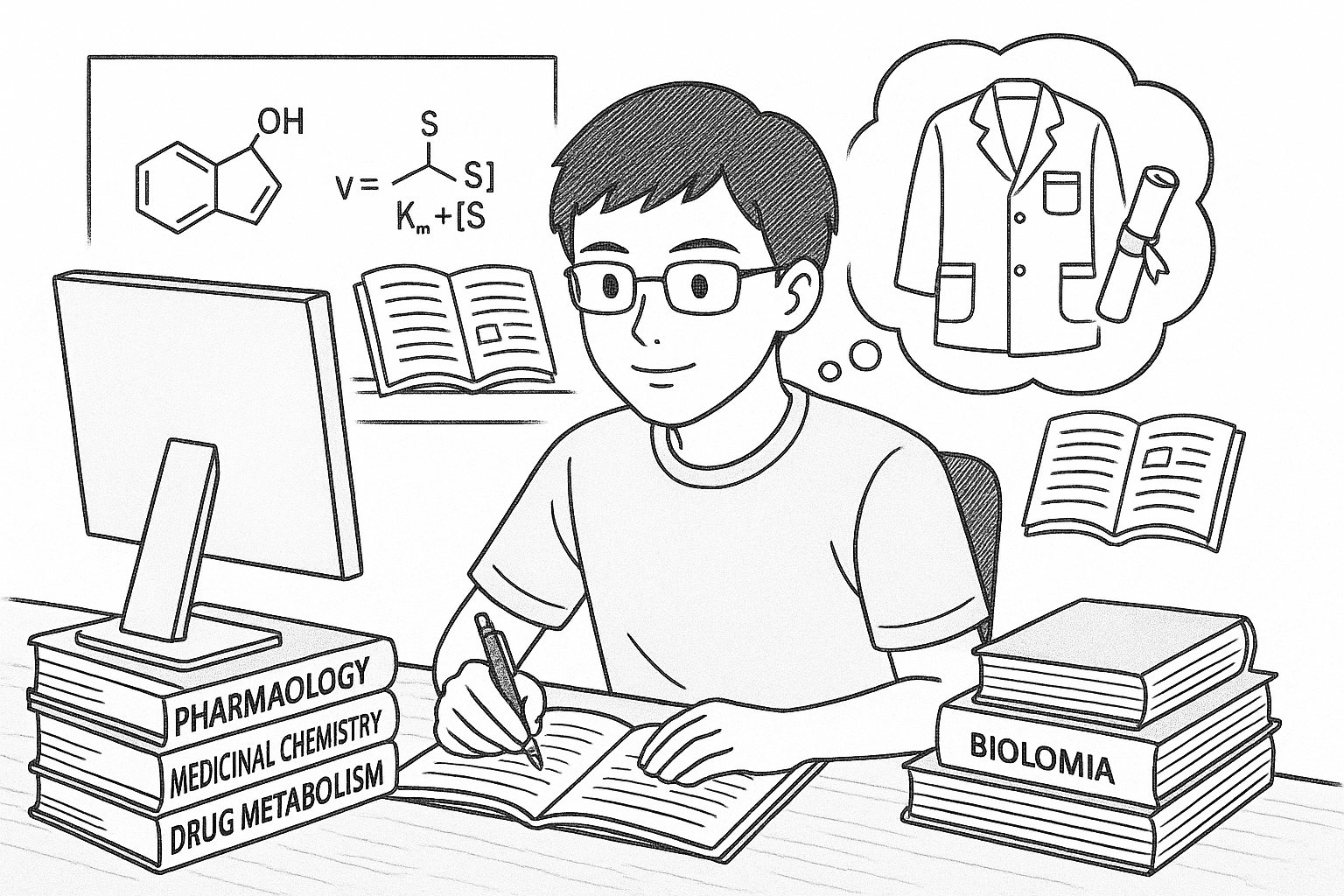
もともと文系寄りの私が薬学部を志したのは、高校で出会った薬剤師の先生の言葉がきっかけでした。「病気を診る医師もすごいけど、薬の力で治す道を選んだ」というその一言に強く惹かれ、数学・英語・化学に絞って猛勉強し、公募推薦で薬学部に合格しました。
しかし、理系科目の深い土台がないまま進学した私に、大学の講義はあまりに高い壁でした。1年次の前期でつまずいたのは、「物質の状態」「生体エネルギー」「ヒトの成り立ちと機能調節」「生命情報を担う遺伝子」など、いずれも基礎とされる必修科目。どの授業も内容のスピードが速く、講義動画を繰り返し再生しても理解が進まない。ノートには余白ばかりが増えていき、「勉強の仕方そのものが間違っているのでは」と、次第に自信を失っていきました。
再試・追試が重なった頃には、もはや「薬剤師になれるかどうか」以前に「この大学生活を乗り越えられるのか」という不安の方が大きくなっていました。
そんな私が変わるきっかけとなったのが、2年次進級のタイミングで出会ったウェルズの個別指導でした。初回面談で担当の先生は、私のテスト答案やレポートを広げながら「これは高校の基礎が抜けたまま、いきなり大学内容に飛び込んでしまったパターンだね」と明確に分析。その言葉に、心の奥底で感じていた不安が言語化された気がしました。
そこから、週2回の対面指導と週1回のオンライン質問対応がスタート。最初の数か月は、大学の講義を追うことよりも、高校範囲の「化学基礎」「生物基礎」の理解を一から総点検しました。構造式や代謝経路、エネルギーの流れなどをすべて図に書き出し、「なぜそうなるか」を言葉にして説明する演習を繰り返しました。知識を暗記で積み重ねるのではなく、「理解→記憶→応用」という順で構築する学び直しでした。
先生はいつも、「理由を説明できない知識は試験本番では使えないよ」と言いました。ノートも「考え方→公式→例題→応用問題」という流れで整理され、直前期には応用問題から逆にさかのぼる“逆流復習”で、理解の穴を一つずつ埋めていきました。
また、学習計画はGoogleスプレッドシートで日々共有。起床・就寝、学習内容、理解度などを記録し、生活リズムと学習を連動させることで、「今やるべきこと」が常に明確になっていました。この日々の蓄積が自信となり、追試にはすべて合格。その成功体験をきっかけに、かつて最も苦手だった薬理学が「得意科目」に変わりました。
それからの大学生活では、毎年課題にぶつかりながらも、ひとつずつ「理解して乗り越える」経験を積み重ねました。6年目の卒業試験では成績上位で通過し、国家試験も一度で合格。基礎がボロボロだった私が、今こうして新人薬剤師として働けているのは、苦手に正面から向き合い、「やり直す勇気」を持てたからです。
理系未経験でも、苦手が多くても、正しい方法で積み直せば、未来は必ず変えられます。私は6年間かけてそのことを学びました。今、苦手に押しつぶされそうになっている薬学生がいたら、声を大にして言いたい。遠回りは、無駄じゃない。理解して積み重ねることで、苦手は必ず武器になります。