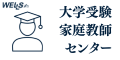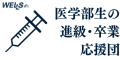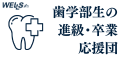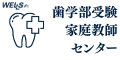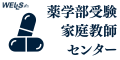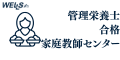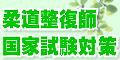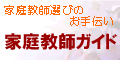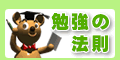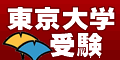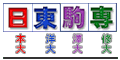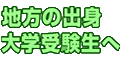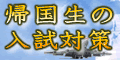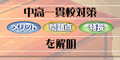【東北薬科大学 薬学部 4年生】 仙台の春の訪れ

東北薬科大学薬学部の4年生だった春。模試の点数が思うように伸びず、卒業試験が目前に迫る中、私は仙台の下宿から実家へ電話をかけました。「物理化学も生物も分からない。もう進級できないかもしれない」と、受話器越しに声を震わせながら泣きついたのが、すべての始まりでした。
高校までは暗記中心の勉強でそれなりに結果が出ていた私にとって、「考えて解く」という大学の問いかけはあまりに厳しく感じられました。講義ノートを読み返しても、反応式や代謝経路のつながりがつかめず、過去問の選択肢も見た瞬間に頭が真っ白になる。1年次、2年次で進級を逃しかけた記憶が繰り返しフラッシュバックし、眠れない夜を何度も過ごしました。
そんな私を見かねて、家族が紹介してくれたのが、ウェルズの個別指導でした。初回面談で出会った先生は、私の答案や小テストを並べて色分けしながらこう言いました。「知識が点で止まっているから、線にしていこう」。その言葉に、不思議と緊張がほぐれたのを覚えています。
そこから、週2回の対面授業とオンライン質問対応が始まりました。先生はまず、反応機構や代謝経路を「図で描いて説明する」ことを徹底させました。紙に書いたスキームを前に、口頭で「なぜこうなるのか」「次に何が起こるのか」を説明し、理解が曖昧な部分はすぐに洗い出されました。暗記に頼ろうとすると、「それはなぜ?」「言葉にできる?」と返され、はじめのうちは戸惑いばかりでした。でも、点だった知識が線に変わっていく手応えが日に日に増していき、不思議とノートに書く量は減っているのに、内容への理解は深まっているという実感がありました。
また、学習だけでなく、生活管理の仕方も大きく変わりました。得点推移や演習正答率、さらには毎日の睡眠時間までを同じGoogleスプレッドシートに記録し、先生と共有。得点が上がり、寝不足が減ると、グラフも自然と右肩上がりになっていく。その目に見える変化が励みになり、「できることを、今日やる」という姿勢がようやく身についていきました。
迎えた卒業試験では、以前は白紙提出すらあった物理化学の問題にも、「考えて解ける」という感覚がしっかりと根づいていました。生物系も、代謝経路の意味やつながりがイメージとして浮かび、「なぜその選択肢が違うのか」を自分の言葉で説明できるようになっていたのです。結果は、無事に全科目合格。そして、そのまま国家試験の準備に突入し、最初で最後の本番で合格することができました。
いま私は、実家が営む薬局で患者さんと向き合っています。服薬指導の場で、相互作用を説明したり、副作用の仕組みを伝えたりするとき、大学時代に苦しみながら身につけた「知識をつなげて考える力」がそのまま活きていることを実感します。成分名が違っても作用機序で結びつけられるようになったのは、あのとき“理解で学ぶ”姿勢に切り替えたからにほかなりません。
もし、あの春に電話をかける勇気がなかったら――きっと今、私は白衣を着ることも、患者さんと向き合うこともできなかったでしょう。暗記だけでは乗り越えられない薬学の学びの中で、思いきって助けを求め、理解を深める方法を身につけたことで、私はようやく「自分の力で解ける自分」になれたのです。
いま、不安で立ちすくんでいる薬学生がいるなら、伝えたいことがあります。知識はつなげて初めて意味を持つ。その力は、ただ合格するためではなく、現場で生きる力にもなります。勇気を出して、考える学びに一歩踏み出してください。それは、あなたの未来を確実に変えてくれるはずです。