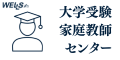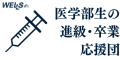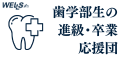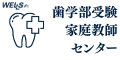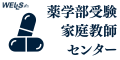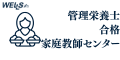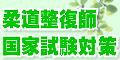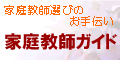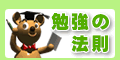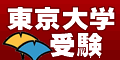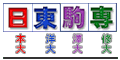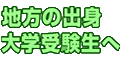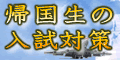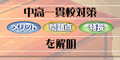【文系 千葉科学大学 薬学部生】薬理を武器に国家試験合格へ
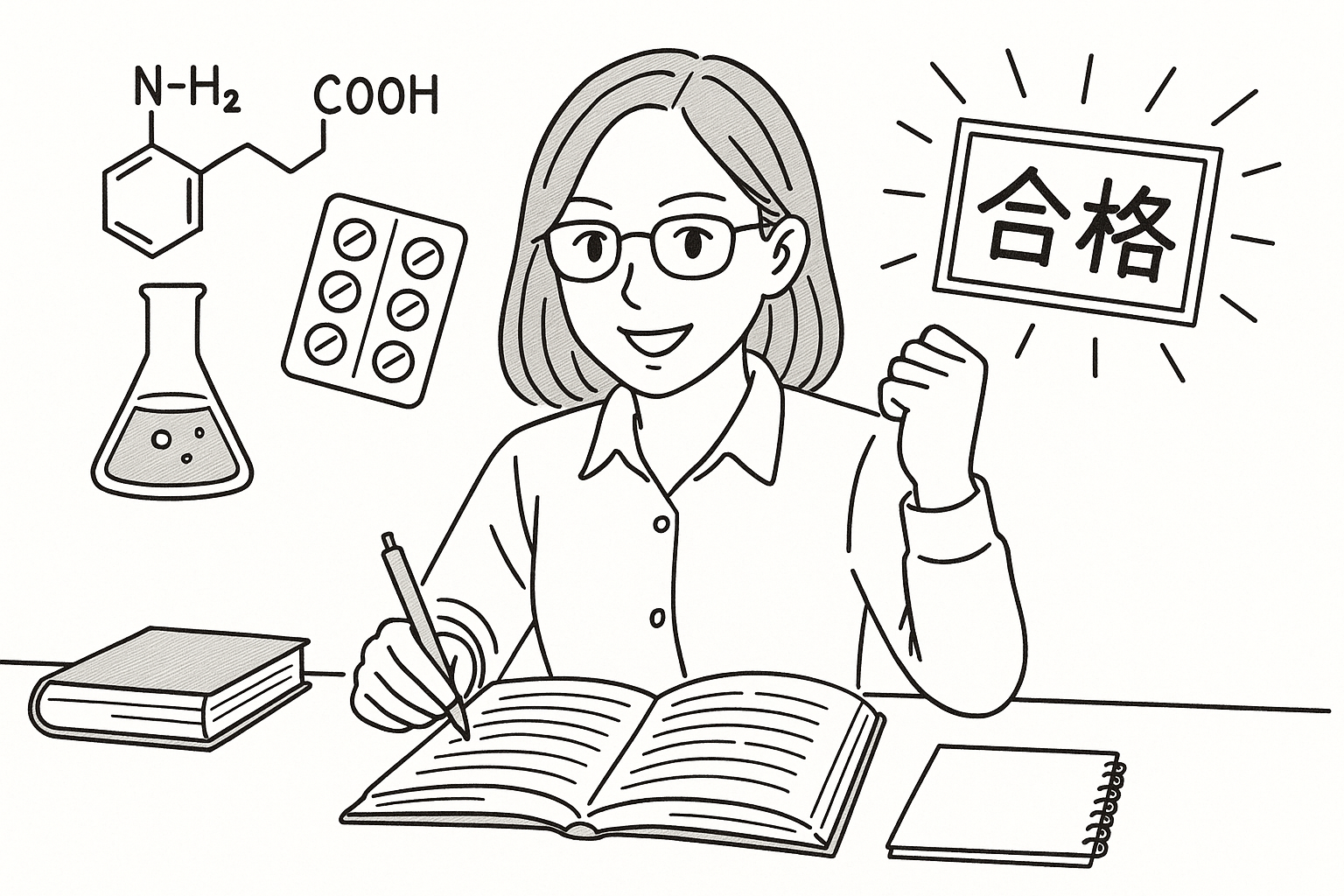
浪人の末に、もともと目指していた経済学部から理転し、千葉科学大学薬学部に特待生として入学した私。理系未経験に近い状態での挑戦でしたが、1年次はなんとか乗り切り、学年10位に入る健闘を見せました。周囲からも「順調なスタートだね」と言われ、自分でもこのまま上位をキープしていけるはずだと信じていました。
しかし、2年次に入ってすぐ、流れは一変します。有機化学や生化学の講義では、黒板の数式や構造式が目に入った瞬間から意味が取れず、開始5分で頭が置いていかれる感覚。高校では物理を選択しておらず、化学も有機の後半はほぼ独学のまま受験を終えていた私にとって、知識の下支えがないまま本格的な薬学専門科目に放り込まれたことは、想像以上に厳しい現実でした。
気がつけば複数科目で単位を落とし、追試・再試の山に埋もれ、ノートを開いても内容が頭に入らず、勉強の習慣さえ崩れていきました。「こんなはずじゃなかった」と焦るばかりで、何に手をつけてもすぐに自信を失い、毎日が空回りするようになっていったのです。
転機が訪れたのは、2度目の春でした。ウェルズの先生との初回面談。私の過去問と答案を机に広げながら先生は、淡々とこう言いました。「穴は2か所。高校物理化学の基礎と、アウトプット不足」。曖昧な励ましではなく、明確な分析と方針提示。その瞬間、どこかで止まっていた時間が動き出した気がしました。
そこから、週2回の対面指導が始まりました。まずは高校範囲の物理と化学を徹底して洗い直し。公式の導出や現象の意味を、黒板の板書ではなく、私の口で一つずつ説明させるスタイルで進められました。数式を“型”で覚えるのではなく、現象の順序を言語化して再現する。正直、最初はしんどかったですが、演習を繰り返すうちに数式が意味を持ち始め、次第に「だからこの計算式になるんだ」と納得しながら解けるようになりました。
並行して、有機化学・生化学・微生物学などの再試験対策も進行。単元ごとに分割し、毎回の演習後に要点を口頭でまとめ、自分の言葉で説明できない箇所は次回までに整理しておくという“発信ベース”のルールを徹底しました。紙に書くだけの勉強では得られなかった「定着感」が生まれ、知識が頭に貼り付いていく感覚を初めて味わいました。
意外だったのは薬理学の変化です。当初は得意でも何でもなかったのに、物理化学や生化学の基礎が固まり始めたタイミングで、「薬理が他分野をつなぐ橋渡しのような位置にある」と気づき、一気に興味が湧きました。過去問演習を重ねるうちに得点源に化け、気がつけば一番自信のある科目になっていました。
結果として、3年後期は再試験ゼロで進級。卒業試験も一発合格で通過。国家試験本番では、薬理がまさかの満点。全体の得点も安全圏に届き、薬剤師免許を手にすることができました。何より大きかったのは、本番中に問題を読んだ瞬間、「ここは薬理で確実に取れる」「この範囲は有機で抑える」と、自分の中に戦略があり、解く順番を選べる自分に変わっていたことです。
得意科目をとことん伸ばし、それを軸に苦手を底上げしていく――先生のこの指導戦略は、まさに私にフィットしていました。もし当時、苦手ばかりを埋めようと自己流で焦っていたら、知識は今でも点のままだったと思います。強みを見つけ、それを活かして弱点を補っていくという学び方が、私の未来を変えてくれました。
いま、薬剤師1年目として調剤室に立つ毎日。患者さんの疑問に答える中で「あの公式の意味はこういうことだったのか」と気づく瞬間が連続しています。大学での学びが現場に直結している実感。それは、あのとき“意味でつなぐ学び”に切り替えたからこそ得られたものです。
焦りで視界が曇っている薬学生がいたら、どうか思い出してほしい。得意は、あなたの最大の武器になる。それを信じて伸ばせば、苦手は必ず追い付いてきます。