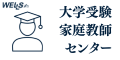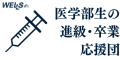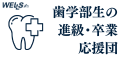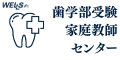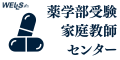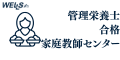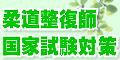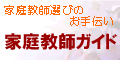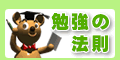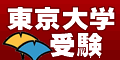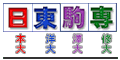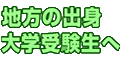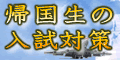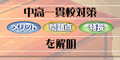薬学部 卒業対策〜卒業に向けた学習と生活のポイント〜
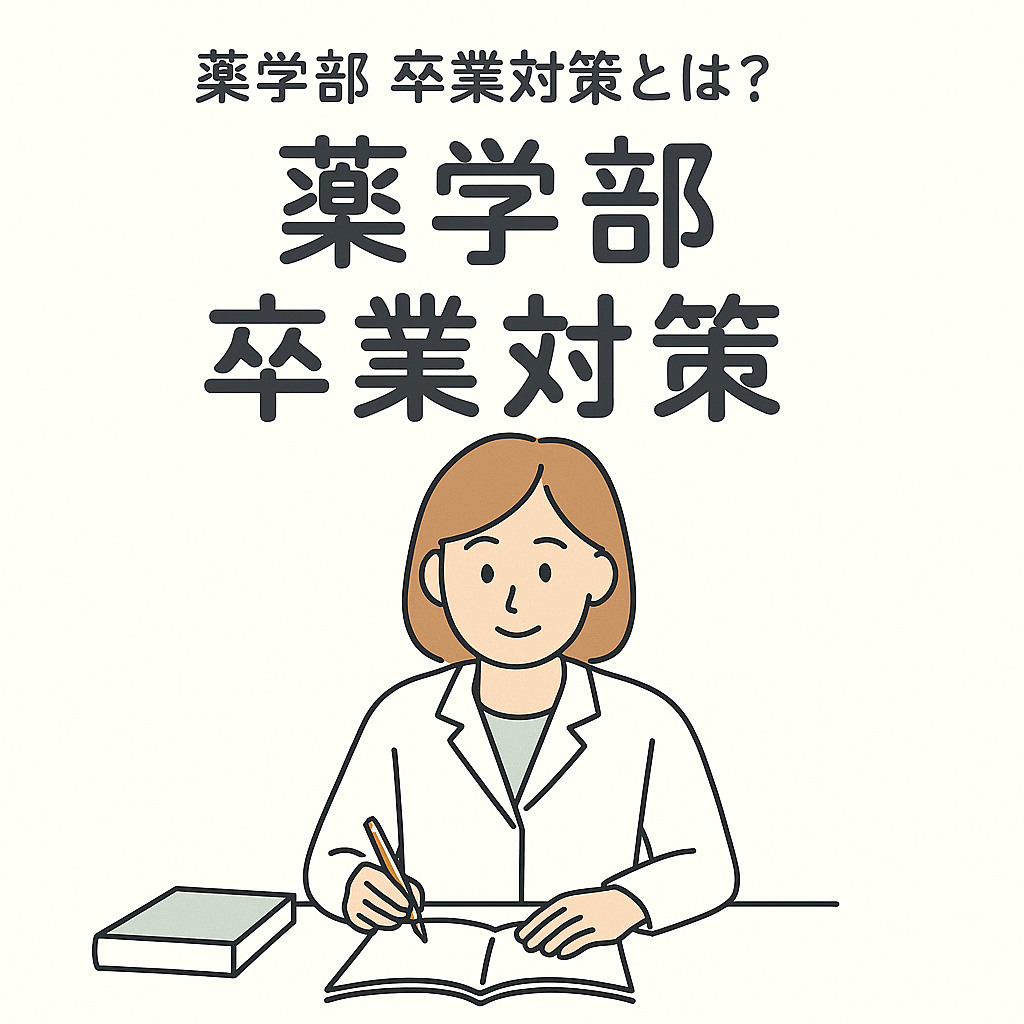
薬学部6年間の学びの集大成が「卒業判定」です。進級テストや必修試験を乗り越えた学生にとっても、卒業を確実に迎えることは決して簡単ではありません。特に近年は薬学教育モデル・コアカリキュラムの改訂やOSCE・CBTの位置づけ強化などもあり、卒業要件を満たすためには計画的な対策が不可欠です。ここでは、卒業に向けた勉強法や生活習慣、スケジュールの立て方について、具体的に紹介します。
卒業対策の基本的な考え方
卒業判定のカギは「必修科目の単位取得」と「卒業試験の突破」です。国家試験対策とも重なる部分は多いですが、卒業に焦点を当てた場合、次のようなポイントを押さえることが大切です。
- 単位を落とさないことが最優先 卒業に必要な必修科目の単位を落としてしまうと、留年や秋卒の可能性が生じます。国家試験の前にまず「卒業できること」を最優先にしましょう。
- 大学ごとの卒業試験の特徴を把握する 出題範囲や形式は大学ごとに異なります。過去問や先輩からの情報をもとに、出題傾向を早めに掴んでおきましょう。
- 国家試験と並行して対策する 多くの大学では卒業試験の水準が国家試験と近く設定されています。そのため、卒業試験対策を進めながら国家試験に直結する学習を同時に行うことが理想です。
必修科目の対策
卒業要件に直結するのは必修科目です。特に注意すべきは以下の科目です。
- 薬理学・薬剤学・病態・治療 配点が大きく、臨床に直結する重要分野。薬効・副作用・相互作用を整理し、疾患ごとに薬物療法をまとめておくと効率的です。
- 物理化学・生化学・薬物動態 苦手とする学生が多い分野ですが、公式の丸暗記ではなく、現象を理解しながら問題演習を重ねることが大切です。
- 衛生・法規 暗記中心の分野ですが、出題頻度が高いため軽視は禁物。過去問を繰り返して定着させましょう。
勉強法の工夫
(1) 過去問演習の徹底
卒業試験は大学独自の問題も出題されますが、過去問の傾向は強く反映されます。過去5年分を最低でも3回は解き直し、出題傾向を肌感覚で掴みましょう。
(2) 苦手分野の集中特訓
自分の弱点を曖昧にせず、科目ごとに「確実に点を取れる範囲」を増やしていくことが重要です。全分野を広く薄くやるより、苦手を潰す方が得点力は伸びます。
(3) アウトプット型学習
「読む」「聞く」だけでは定着が弱いです。ノートまとめや図解、友人への説明など、アウトプットを中心にした学習を取り入れましょう。
スケジュール管理
(1) 年間の流れ
- 4〜6年生前半:必修科目の履修を落とさず、日々の授業とテストをクリアする
- 6年生夏〜秋:卒業試験の範囲を把握し、過去問演習と弱点克服に着手
- 6年生冬:卒業試験直前期に集中的に演習、国家試験対策と併行
(2) 1日のルーチン
- 午前:暗記分野(法規・衛生・薬理の薬効分類など)
- 午後:計算系(薬物動態・薬剤・物理化学)
- 夜:その日の復習、暗記カード確認
1日7〜8時間を目安に、無理なく継続できるペースを保ちましょう。
メンタルと生活習慣の整え方
卒業試験前は精神的に追い込まれる学生が多いです。モチベーションを保つ工夫も欠かせません。
- 仲間と勉強する 模擬試験や小テストを友人と一緒に解くことで競争心と協力心が生まれ、孤独感を減らせます。
- 生活リズムを安定させる 本番は朝から試験が行われるため、毎朝同じ時間に起きて頭を働かせるリズムを整えておきましょう。
- 小さな目標設定 「今日は薬理の循環器だけ」「この週は法規を全部復習」など、短期的なゴールを設定することで達成感を積み重ねられます。
よくある失敗と注意点
- 国家試験対策ばかりに集中して卒業試験を軽視する
- 暗記に偏り、理解を伴わない学習になる
- 不安から参考書を増やしすぎて消化不良になる
必要以上に教材を広げるより、信頼できるテキストや過去問に絞って繰り返すことが成功の秘訣です。
まとめ
薬学部の卒業対策は「国家試験合格」の前提となる大切なステップです。
卒業試験は決して形式的なものではなく、薬剤師として必要な知識と理解度を問うものです。
- 必修科目を落とさない
- 過去問と弱点克服を徹底する
- 規則正しい生活で心身を整える
この3つを軸に計画的に取り組めば、卒業は決して難しいものではありません。
「卒業すること」そのものがゴールではなく、国家試験合格・薬剤師としての未来につながる大切な通過点です。焦らず、一歩ずつ確実に積み重ねていきましょう。